中国: +86-18276690090
中国: +86-13457678957

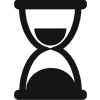 ツアーをオーダーメイドする
|
 柔軟性を最大限に活用
|
 ご満足いただけることを保証
|
 自分の中国物語を生きる
|